近頃、情報番組を見ていると「タイパ」という言葉をよく耳にします。
『タイパ?聞いたことあるけど詳しくは分からない?』
『タイパってどんなとき使う言葉?』
上記のような疑問を抱いたことはありませんか?
そんな疑問を解決することで、Z世代(1990年後半~2012年頃生まれた世代)の人とも距離が短くなるのではないでしょうか。
言葉を短くするのが当然のような時代になってきています。
本記事でタイパについて、詳しく解説していきますので最後までご覧ください。
本記事のポイント
- タイパの意味・発祥
- 重視されるようになった理由
- コスパ・スペパの違い
- メリット
- デメリット
- 使い方例
タイパって何?
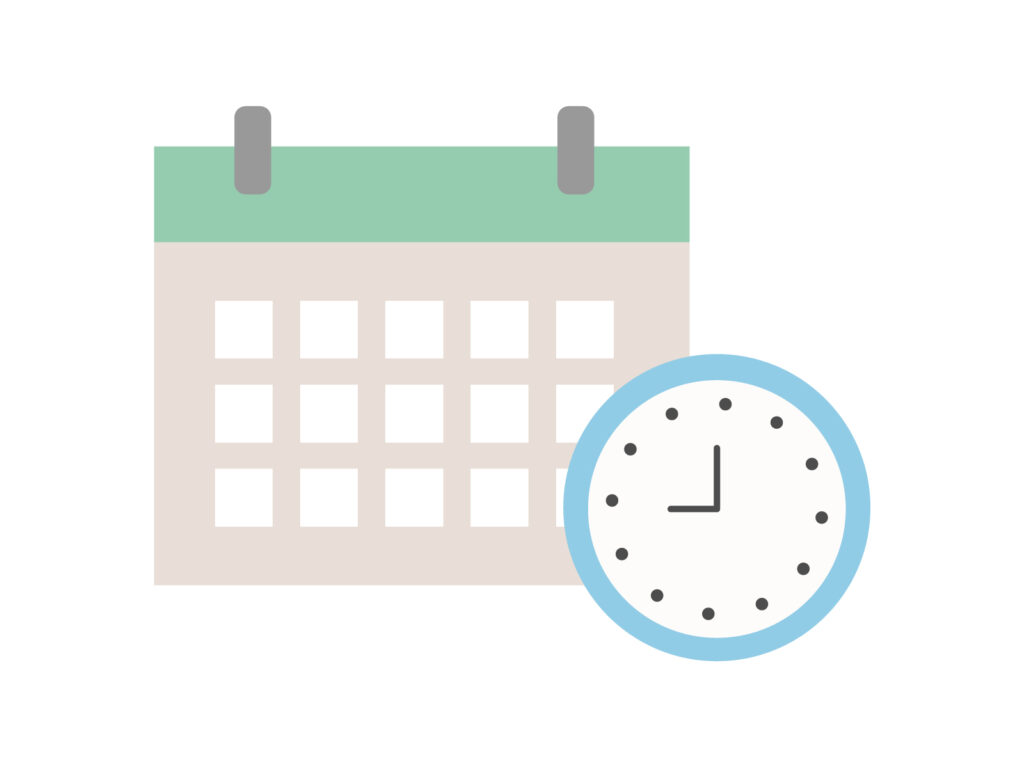
なんでも言葉を短縮するのが時代と共に変化してきています。
タイパもその中の一つです。
いったいどのようにして生まれた言葉なのでしょうか。
タイパの意味
タイパとはタイムパフォーマンスの略した言葉になります。
費やした時間に対する満足度の度合いを示す言葉です。
タイパは短い時間でどれだけの効果と満足度を得られるのかを重視しています。
タイパのことばの発祥は
タイパの発祥は1990年後半~2012年生まれのZ世代からの流行が発祥となります。
この世に生まれたときから、デジタル機器やAT技術に囲まれて育って来ている世代なので、短時間で効率の良い情報を収集することがあたりまえです。
タイパは2022年に三省堂主催の今年の新語として大賞にも選ばれている言葉なので、多くの人に浸透していったのではないでしょうか。
タイパが重視されるようになった理由

タイパが重視されるようになったのは、Z世代からの影響と言われています。
下記のような状況から重視されています。
時間に対する意識の変化
タイパはZ世代に限らず、ビジネス社会においても必要不可欠です。
時間の意識の背景にはいくつかあります。
*如何に効率よく情報を得たい。
*短時間で効率的に時間をかけたものと同等の成果を得たい。
*社会のトレンドにのり遅れたくない。
上記のように時間の意識が変化していくのは、職場の環境や勉強をする場などでもタイパに対する意識を高める要素だからです。
Z世代の行動にはそれぞれ違いがありますが、一般的にはデジタル機器に対する依存度や社会的な意識の高さを持っています。
経済不況の中で育っているZ世代は将来のことを考えている人が多く、貯蓄や節約に高い関心があるのです。
例えば商品の購入やサービスを契約するときは、SNSなどを活用してじっくりと情報収集をしてから消費行動をとります。
また動画などを見るときは1.5倍速で、鑑賞するという行動をとるのです。
ビジネス社会に於いてもタイパを意識する人々の背景には、デジタル化による価値観の違いが変化してきているように思います。
デジタルやITの技術が発展
スマホやパソコンが普及しインターネットにより、誰でも簡単に情報を得られるようになりました。
タイパが重視されるようになったのは、効率よく情報を取集して時間を有効活用したいという意識からです。
一定時間内で多くの情報を取捨選択して効率を高めるために、デジタル技術が開発されています。
タイパはデジタル機器やIT技術が発展した為にできた言葉ではないでしょうか。
Z世代の行動パターン
Z世代の行動は様々ですがSNSの活用が当然のようで、体験したことを共有するのがあたりまえになっています。
例えば物を買うにしてもSNSでどこが安いか、品物のレビューなどを見て購入します。
どんなことでも直ぐに共有するのが、Z世代の特徴です。
動画も短時間で鑑賞することや、美の意識が高く世の中に出回っているものは、Z世代からの発信も多く見受けられます。
経済にも多くの影響がでているようです。
世代の違いはともかく見習うべき行動もあるのではないでしょうか。
タイパ・コスパ・スぺパの違い
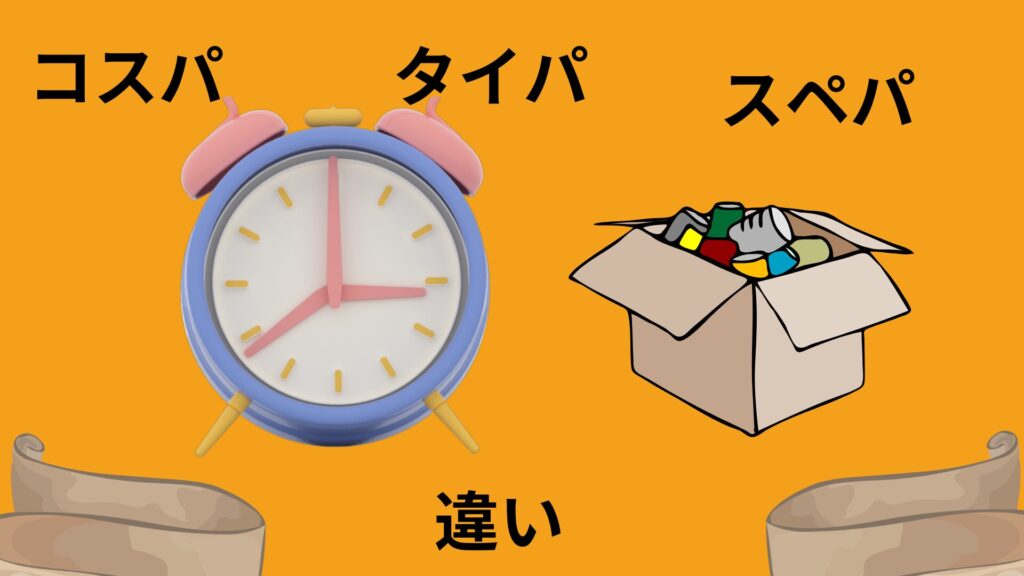
タイパはすでに述べましたように、短い時間で効率の良い情報を得るときに使われる言葉です。
コスパとスペパとの違いはどのようなのか見ていきましょう。
コスパとは
「コスパ」とはコストパフォーマンスを略した言葉です。
ある製品やサービスが提供する性能や利益と、価格やコストのバランスを指します。
「コスト」はある活動を実行するにあたり、必要な費用や負担のことです。
その活動の費用を少しでも下げることで、「コスパが良い」と使われます。
スぺパとは
「スペパ」とはスペースパフォーマンスを略した言葉です。
日本語に訳しますと「空間対効果」と言う意味で、つまりスペース(空間)活用の効率の良さを示します。
コストパフォーマンスから派生した概念で、空間の使い方を評価する際に使われる言葉です。
タイパ、コスパやスペパは「時間・価格・利益・空間」を表した言葉になり、すべて取り入れることでもっと効率が良くなるのではないでしょうか。
タイパのメリット
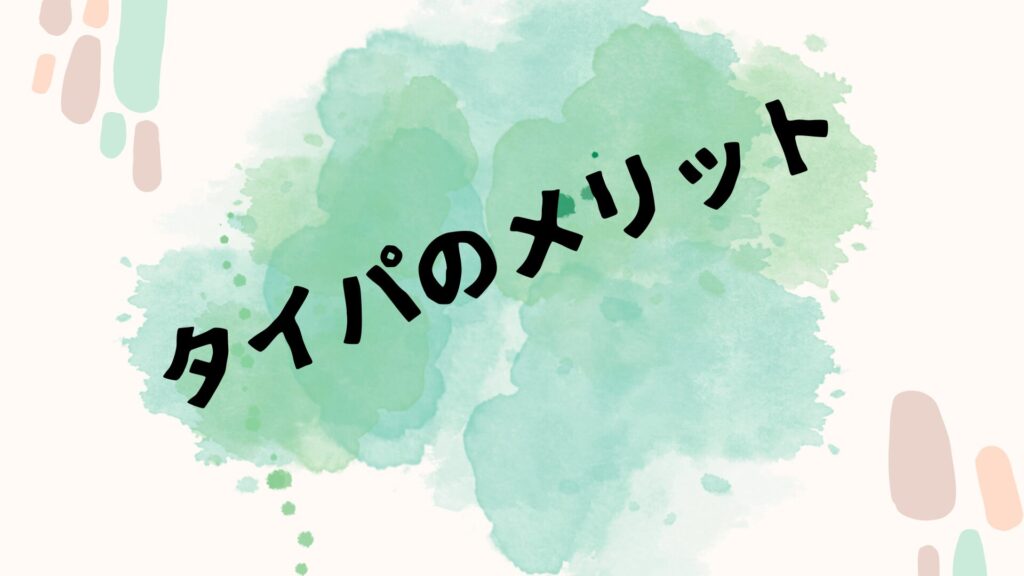
タイパのメリットとはどんなことがあるのでしょう。
時間の効率化
タイパは時間を効率的に使えることがメリットです。
短い時間で多様な情報や効果が得られることで、他の物や行動を試すことができます。
早く仕事が終わった分有効に活用できる時間ができるということです。
様々な働きかたや行動
タイパのメリットとして、ビジネスでは働き方改革によって残業をすることが難しくなっています。
先にも述べましたがタイパを重視している人はできるだけ短い時間で、仕事を終えることで自分の時間を有効活用したいと思っているのです。
働きかたも変わってきましたが、それぞれ考え方も変わってきているのではないでしょうか。
仕事中心に考える人、プライベート時間の取り方を中心に考える人などで今後の働き方の行動が変わってくるのではと思います。
Z世代から注目される
Z世代からは就職活動も「タイパ」を重視している企業が注目されています。
ビジネスでは時間を効率よく使うことで、生産性が上がっていき企業自体も大きな影響が出ているのです。
例えばパソコンの自動計算や自動入力などのツールを使うことで、仕事が捗るためタイパと言えます。
大企業では各地域の会社とWeb会議をするのが、普通になっている所が多いです。
オンラインですべて解決できるのが良く、タイパと考えられるためZ世代に注目されるのではないでしょうか。
タイパのデメリット
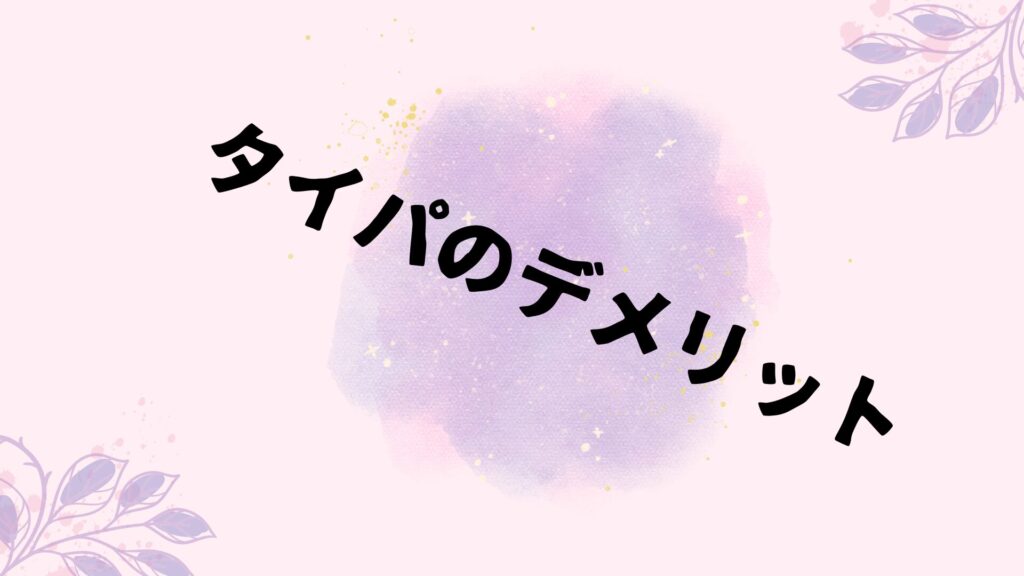
タイパのデメリットは時間短縮による落とし穴があります。
時間を気にする
デメリットの一つとして、決められた時間内で情報や作業をしなくてはいけないので、時間ばかりきにしてしまうことです。
時間を重視するため、大事な情報の取りこぼしが起きてしまう可能性があります。
目的が曖昧
短い時間でやった気になってしまい、目的が曖昧になってしまうのもデメリットです。
タイパを重視しすぎると過程が楽しめない傾向があるので、気をつけなければいけません。
また、結果重視の考え方ですと目的を見失うため成長度も低くなる可能性があります。
楽しめない
時間対効果を求めるあまり、過程を楽しめないことが考えられます。
タイパで作業してよい結果が出たとしても、途中経過が楽しめないのがデメリットです。
効率よく作業をするにしても経過は楽しみたいのですよね。
タイパの使い方例

タイパの言葉の使い方例
タイパの言葉は主に家事や仕事、勉強などの物事が短時間で解決した場合に「タイパが良い」と使うことがあります。
タイパの事例
普段の生活の中でタイパを高めるには、どのようなサービスを利用して充実した日々を送るかが重要になります。
下記は主な事例です。
□動画を倍速にして、視聴するのはタイパを高める代表的な事例
□冷凍食品やデリバリーを利用する事例
□Webでセミナーを行う事例
□本の要約サービスで例として「フライヤー」という1冊の本を10分で理解できるサービス事例
上記のようなことは通常に行っているという方も多いのではないでしょうか。
まとめ
近年ではタイパはあたりまえの時代です。
時間を効率よく使うことがタイパの意味なので、毎日の生活で知らないうちにタイパを利用していることがお分かりいただけたのではないでしょうか。
*「タイパ」の発祥は1990年後半~2012年生まれのZ世代からの流行が発祥
*時間に対する意識の変化
*デジタルやITの技術が発展
*Z世代の行動パターン
*コスパとスペパの違い
*タイパのメリットデメリット・事例
上記の内容を解説してきました。
参考になれば幸いです。
PR
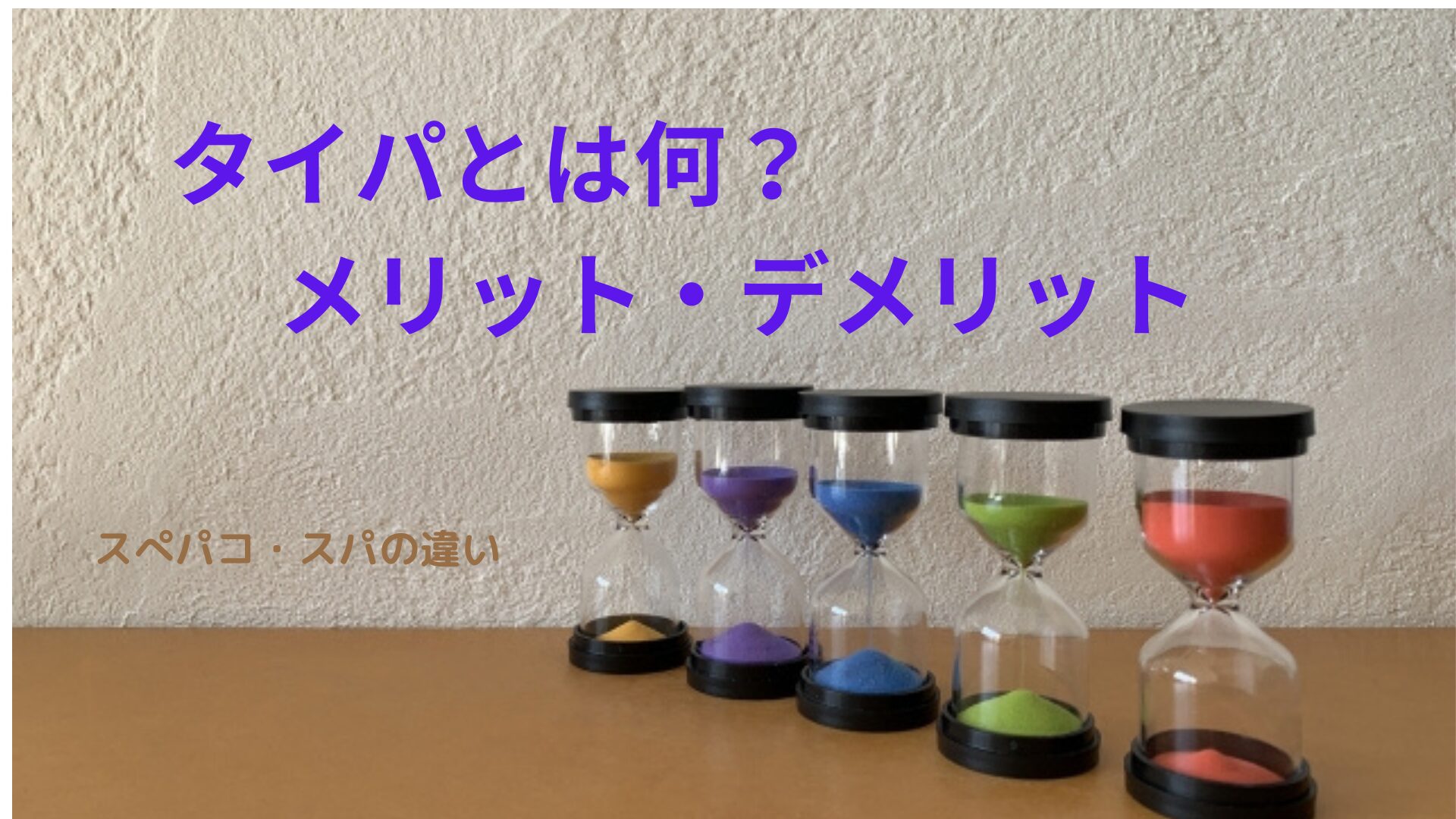
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/325df7dd.2adc5652.325df7de.bb4664f3/?me_id=1285657&item_id=12877658&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookfan%2Fcabinet%2F01084%2Fbk4299048733.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



